今日は月曜日だが、世間的には「成人の日」の祝日でもあった。この日も空は晴天で、外を歩くにはそこまでに寒くはない感じ。わたしは毎週の月曜日のように「ふるさと公園」へと歩くのだった。
そしてこの日の「ふるさと公園」で、わたしはずいぶんと久しぶりにカワセミに出会ったのだった。この公園でカワセミの姿を見るのは24年の4月以来のことになり、もう「ふるさと公園」にカワセミが来ることもなくなるのかと思い込みそうになっていたところだ。そのあいだに毎週のように三脚を立ててカワセミを狙っていたカメラマンの方々(約2名)も公園に来なくなってしまっていた。そんなとき東京の都心でカワセミの姿が見られるようになったというニュースも流れ、この公園のカワセミが東京都心へ引っ越してしまったのか、な~んて考えたりもしたのだったが。
ただ、「鳥の博物館」が半年ごとに発行している「鳥だより」をみると、手賀沼の観測でカワセミは毎月3~4羽は見られていたようなので、偶然わたしの目にとまっていないだけのことだろうとは思っていたが。
それでこの日は、池のほとりの遊歩道沿いの手すりにとまっているユリカモメを見ていたら、その同じ手すりにカワセミもとまっていたのだった。


このあとは偶然にわたしの行く方向にカワセミも飛んで来て、さいごに見失ったと思ったら、池沿いの木の枝からカワセミが池へダイヴするところを見ることができた。一瞬で水面からまた飛び上がってしまったが、果たしてカワセミくんにハンティングの成果があったのかどうかはわからなかった。
この日は実はコブハクチョウの姿もみられなかったのだけれども、カワセミに出逢えただけで満足ではあった。
「ふるさと公園」から出るところで、すっごい望遠レンズ付きのカメラを抱えられた方が公園に入って行かれたので、「カワセミがいましたよ」な~んて教えてあげようかとも思ったが、それはまさに「余計なお世話」だ。もうカワセミに逢えなかったら余計な期待だけ抱かせてしまうことになる。
しかし、カワセミくんがこれからもこの公園にやって来てくれるといい。やはりカワセミの美しさは「別格」なのだから。
公園を出て、すぐそばのドラッグストアに立ち寄ってみた。わたしは先週ここで「コシヒカリ」を2割引きで買ったわけだが、この日おコメ売り場をみてみると、銘柄米はすっかり売れてしまっていた。みんな、わたしと同じように割引券を使っておコメを買ったわけだなあ。
この頃は「ふるさと公園」の外でも、スズメの姿をよく見かけるようになっていて、スズメの写真を撮るのも楽しみになっている。この日も、われながらなかなかいいスズメの写真が撮れたと思う。


夕方からは「大相撲中継」を見るが、この日はゲストに大相撲ファンの松重豊氏と市川紗椰氏が出演され、解説は元貴景勝の湊川親方だった。湊川親方はまた細身になられて若返られたようで、この日の「成人式」に参加するやんちゃな男の子、みたいではあった。それでも湊川親方の解説は理にかなって「なるほど」と思わせられるし、適度なユーモアも盛り込まれて面白く、これからは相撲中継の大きな「売り」のポイントになるのだろうと思う。
この日も関脇以上の上位陣は関脇の高安に土がついた以外は安泰で、まだ二日目ではあるけれども、先の展開が楽しみではある。
ニュースでは、高市首相が解散総選挙に打って出るという話で持ちきりになっているみたいだ。しかし皆が言っていることだが、この物価高だかの問題山積の今げんざいに政治的空白をつくっていいのか、ということだ。どうも、韓国で旧統一教会の文書内に高市氏の名前が32回も出てきたことが問題にされそうな気配、そんな疑惑をごまかしちゃうための解散総選挙ではないかとも思えてしまう。こういうところは「エプスタイン疑惑」をごまかすためにベネズエラを攻撃したとも言われるトランプ大統領のやり方を模倣するわけだろうか。
ところで、もし今総選挙が行われるとしたら、いくら高市首相の応援団が多いとはいっても、自民党がそれなりに勝てるかどうかは怪しいところだと言われている。まずはこれまでの公明党との選挙協力がなくなるというのがどれだけ影響があるのか。「日本維新の会」がその代わりを果たしてくれるのか。意外と、公明党の影響力というのは大きかったのではないだろうか。
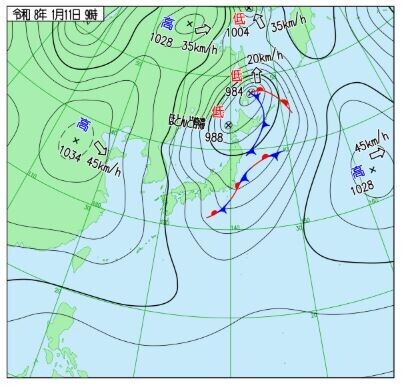

![AKIRA 〈DTS sound edition〉 [DVD] AKIRA 〈DTS sound edition〉 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51+o3Q39RyL._SL500_.jpg)







![千と千尋の神隠し [DVD] 千と千尋の神隠し [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51KX4zMgahL._SL500_.jpg)