このところ、ニェネントくんがしばらく前まで夜にはこもっていたキャットタワーのボックスに入ることがなくなり、キャットタワーのてっぺんで夜を明かすようになった。けっきょくボックスの中が気に入らなくなったのか、それとも、暖かくなったからキャットタワーのてっぺんでもよくなったということなのか、それはわたしにはわからないことだ。
昨夜寝る前に、なぜか60年代のイギリスのバンド「デイヴ・クラーク・ファイヴ」のことを考えていて、彼らがビートルズの『ハード・デイズ・ナイト』に対抗してつくった『五人の週末』という映画のことを思い出していた。
当時デイヴ・クラーク・ファイヴは「ビートルズの一番の対抗馬」と目されていたことがあって、その初期にはイギリスなどではほんとうにビートルズと競っていた。それでライヴァル意識からこの『五人の週末』という映画を撮ったのだけれども、監督はその作品で監督デビューしたジョン・ブアマンなのだった。この映画はもちろん、『ハード・デイズ・ナイト』のような大ヒットにはならなかったけれども、一部の評論家には賞賛された映画なのだった。
デイヴ・クラーク・ファイヴはその後CDの時代にすっかり「忘れられたバンド」になってしまい、知名度もダウンしてしまったのだけれども、これは彼らの曲すべての版権を持っていたリーダーのデイヴ・クラークが、彼らの曲やアルバムのCD再発をいっさい認めなかったためである。デイヴ・クラークは「その方が権利を独占できるから得だ」と考えたらしいが、もちろんそれは「大きな過ち」だった。
そんなことを思い出したり考えたりしながら寝たのだったが、それでしっかりと「デイヴ・クラーク・ファイヴ」のこと、その『五人の週末』という映画のことを夢にみてしまった。
夢では、そんな「観たことのない映画」の、夢で勝手につくりあげられたシーンが繰り拡げられるのだった。
ちゃんと記憶していれば面白かっただろうけれども、目覚めたときにはただ、「そんな夢をみた」ということしか記憶していなかった。
この日も気温が上がり、このあたりでも25℃を超えて「夏日」になったようだ。
午前中に北のスーパーへ買い物に出かけたのだけれども、Tシャツの上にまたシャツをはおった恰好では暑かった。半袖Tシャツだけでよかったのだ。
家のすぐそばで、草の葉に停まったシジミチョウを見つけ、喜んで写真を撮った。
チョウ類の写真はいつも撮りたいのだが、チョウたちは決してじっとしていてくれず、ただ飛び回って写真を撮らせてはくれないのだ。こうやって、葉っぱに停まってじっとしていてくれるチョウは、絶好のシャッターチャンスだ。

このシジミチョウは「ヤマトシジミ」という種類で、日本ではいちばん多く見られるシジミチョウだ。
家に帰ってから調べたら、ヤマトシジミの一生は産卵されて「卵」で一週間、孵化した幼虫で二週間、それがさなぎになってまた一週間かかり、成虫の姿で二週間ぐらい生きるらしい。トータルで六週間の生涯。短いんだなあ。
それでヤマトシジミは、幼虫が食べるカタバミの草の生えるところで繁殖するということ。うん、ウチのそばの空き地には今、カタバミの花がいっぱい咲きそろっているところだ。

今日はスーパーで、安い発泡酒を2缶買ってみた。昼食は先日買った「スイートチリソース」をちょっと使ったスパゲッティをつくってみたが、「まあまあ」の味。とにかく「スイートチリソース」はいっぱいあるので、またやってみようと思う。
食後、買った発泡酒を飲みながら「ちゅらさん」の再放送を見て大笑いする。つづく「虎に翼」は急にシリアスになったけれども、昨日までのコミカルな展開は楽しかった。特に尾野真千子のナレーションにはいつも笑わかされる。
寝る前にパトリシア・ハイスミスの『11の物語』を読む。この夜はさいしょの「かたつむり観察者」だけ。
これって、今よくある「ペット多頭飼育」の崩壊、にも通じるものがあるだろう。いつも読書の感想は別に書いているので、もう何篇か読んだら、まとめて感想を書こうと思う。


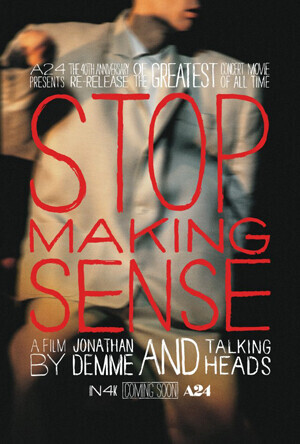




![危険なメソッド [DVD] 危険なメソッド [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Xr1cO77TL._SL500_.jpg)